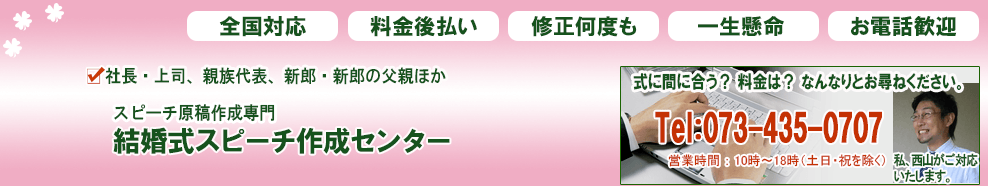私は、話すのが苦手だ。
大学のゼミ発表でも、顔が真っ赤になって声が震えた。社会人になってからも、何度プレゼンを頼まれても「別の人がいいんじゃないかな」と逃げ腰だった。なのに、どうしてこんな大役を引き受けてしまったんだろう。
「由梨、結婚式でスピーチしてくれない?」
親友の真奈美にそう言われたのは、半年ほど前のことだった。
彼女は、私の大学時代からの友達で、寮生活も一緒だった。お互い、親には言えないような恋バナも、卒業してからの失恋も、全部話してきた。気づけば10年以上、どんな時も隣にいた人だった。
「私、他の誰の言葉より、由梨の言葉で祝福されたいんだ」
それを聞いたとき、嬉しくないわけがなかった。
…でも、心のどこかで、違和感があった。
「祝福したい」気持ちはあるのに、それを“言葉”にできる自信がない。
式の3週間前、とうとう不安が爆発した。
会社帰りの電車の中で「結婚式 スピーチ 書き方」で検索していた私の目に、「スピーチ代筆サービス」という広告が飛び込んできた。代筆?ズルじゃないか?そんな思いもよぎった。
でも、クリックしたページにあったコピーが目を引いた。
「あなたの声を、あなたより美しく。語らなかった気持ちに、形を。」
電話番号の下にあった名前――「祝井」。
そのまんまの名前だな、なんて思ったけど、心のどこかで引き寄せられる何かがあった。
気づけば、問い合わせフォームに手を伸ばしていた。
初めての打ち合わせ。カフェで出迎えてくれた彼女は、思ったよりずっと普通の人だった。年齢は30代後半くらい。派手な服装でもなく、声も穏やかだった。
「どうして今回、プロにお願いしようと思ったんですか?」
祝井さんは、そうやって、私の心にまっすぐ入ってきた。
私は、自分でも気づいていなかった心の重りを、一つひとつ話し始めた。
真奈美との大学時代。就職が決まらず落ち込んでいた私を励ましてくれたこと。社会人になってから、仕事が忙しくてしばらく疎遠になったこと。そして、ある小さなすれ違いで、一時期連絡が取れなくなったこと…。
「でも、真奈美は、何事もなかったみたいに“おはよう”って言ってくれて…」
私はそこで、ふいに涙がこぼれた。
「謝れなかったんです。ずっと、言えなくて」
祝井さんは、黙って頷いた。何も言わずに。ただ、ペンを止め、私の目を見るその時間が、ありがたかった。
2回目の打ち合わせで、祝井さんは、初稿を見せてくれた。
「少しだけ読んでみてくれますか?」
私は、プリントされた紙を手に取り、声を震わせながら読み始めた。
「ねえ、あのときの『おはよう』が、私の中でずっと鳴ってるの。
あの一言が、私を赦してくれた。私が何も言えなかったあの日を、
“なかったこと”にしてくれたんじゃなく、“越えてくれた”んだと気づいたのは、
今になってからでした。」
読み終わったあと、私は唖然として言葉を失った。
「……私、こんなふうに思ってたんですね」
「由梨さんが言ってくれたことから、拾い集めて再構成しただけですよ」
「でも…これは、私じゃ書けなかった」
祝井さんは、少しだけ微笑んで言った。
「“あなたの言葉を、あなたより美しく”。あのコピー、気に入ってもらえましたか?」
本番前夜、原稿を抱えて布団に潜り込んだ。声に出して読むたび、段取りではなく**“感情の風景”**が浮かぶ。
彼女と通った学食のカレーの匂い。夜中に語り合った廊下の硬い床。喧嘩した後に目を合わせられなかったあの朝の光…。
そのすべてが、スピーチの中に生きている。
祝井さんは、記憶に地図を描いてくれた。
結婚式当日。
スポットライトに照らされながら、私は壇上に立った。心臓の音が耳に響く。でも、手元の原稿には、「ここで息を吸う」「ここは少し間を」と書かれていた。
それだけで、ずいぶんと安心できた。
私は、ひと呼吸おいて、話し始めた。
「ねえ、あのときの『おはよう』が、私の中でずっと鳴ってるの――」
初めて自分の声が、私のものじゃないように思えた。でもそれは、「他人の言葉」ではなかった。
磨かれた、自分の声だった。
スピーチが終わったとき、真奈美が泣きながら言った。
「ありがとう…あなたに頼んで、本当に良かった」
そのときやっと、私は胸の奥に詰まっていた十年分の気持ちを、手放すことができた。
式が終わって数日後、私は祝井さんにメッセージを送った。
《私、本当に自分の言葉で話せた気がしました。あれは“代筆”じゃなくて、“私自身の再発見”でした》
返信はすぐに届いた。
「嬉しいです。
あなたが伝えたいことは、いつも、あなたの中にちゃんとあるんです。
私は、ただそれを“言葉のかたち”にしただけですから。」
今でも、スピーチの原稿は私の部屋の机にある。
たまに読み返すたびに、あの日の空気が、胸の奥で静かに鳴り始める。
まるで、あの「おはよう」が、今でも続いているみたいに。